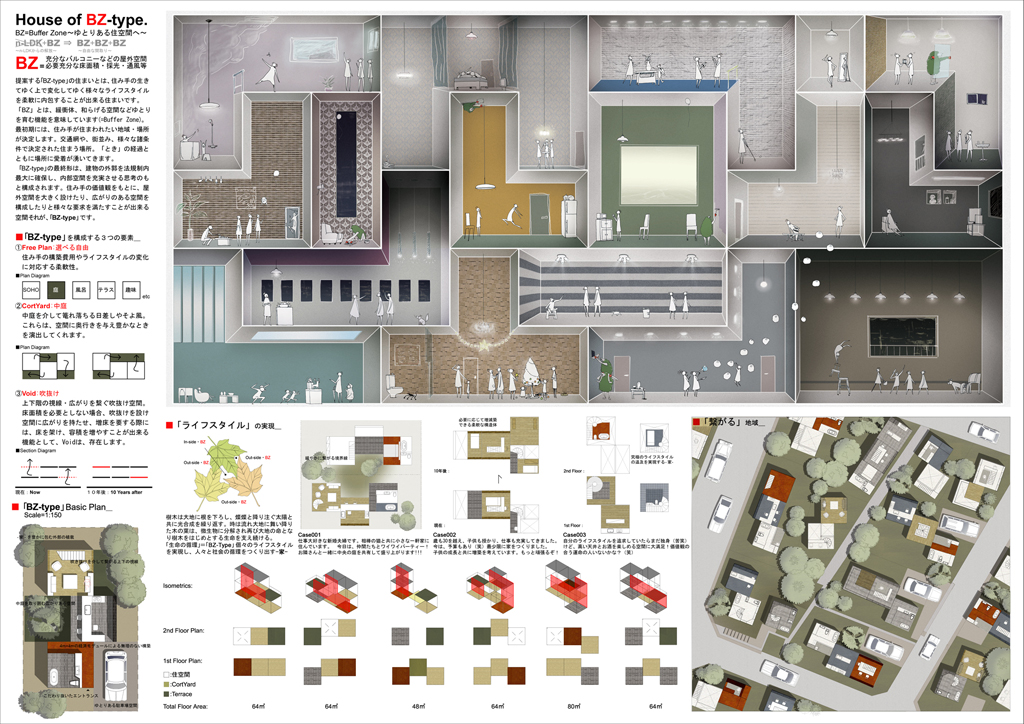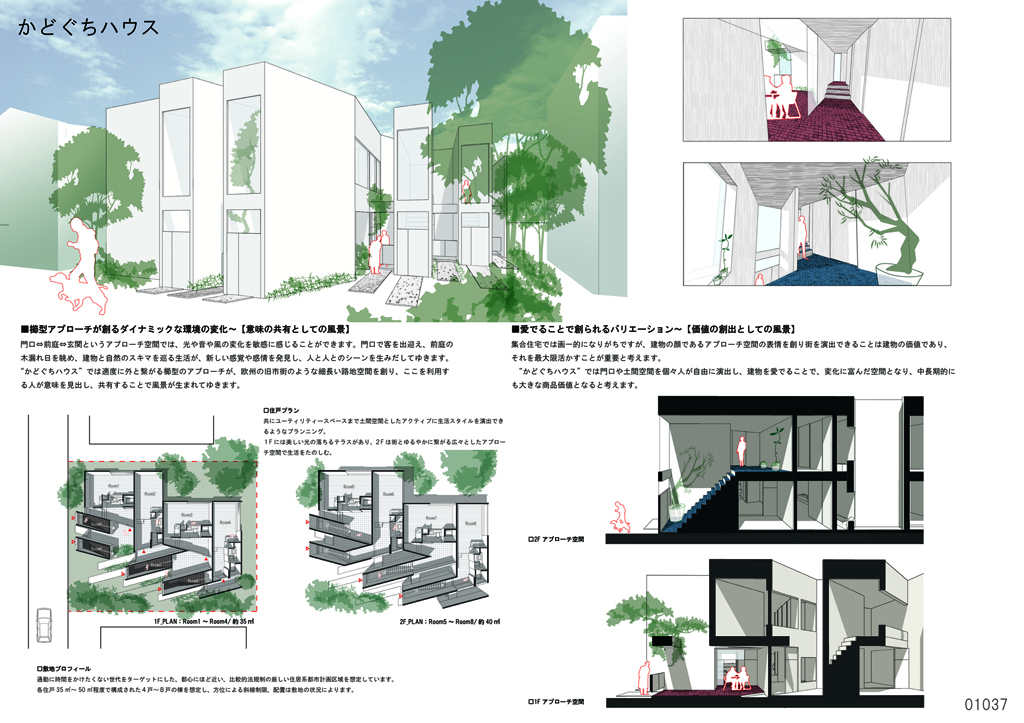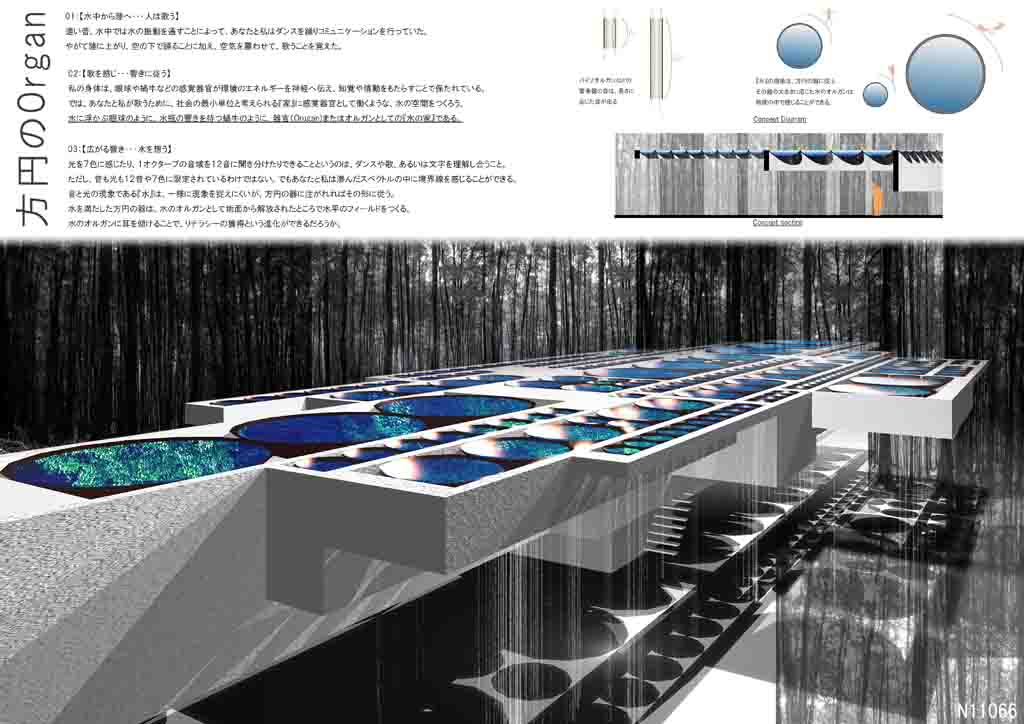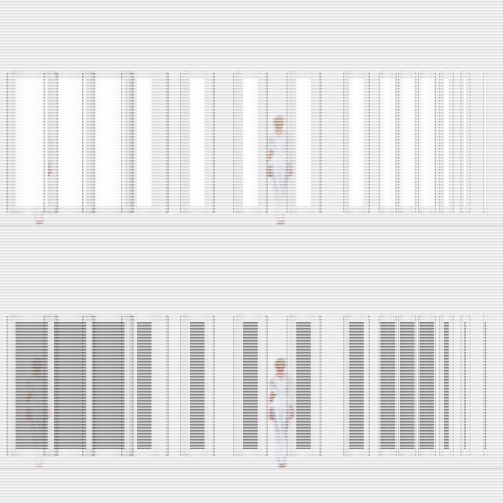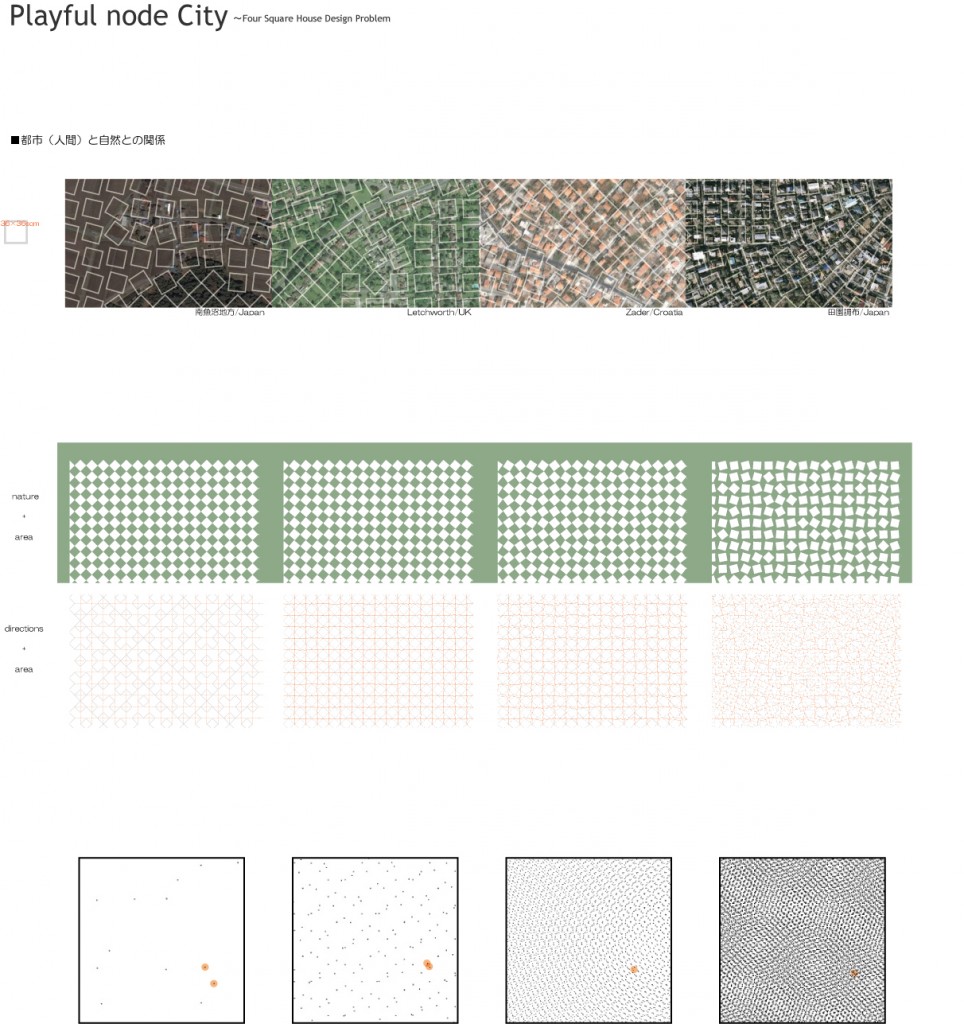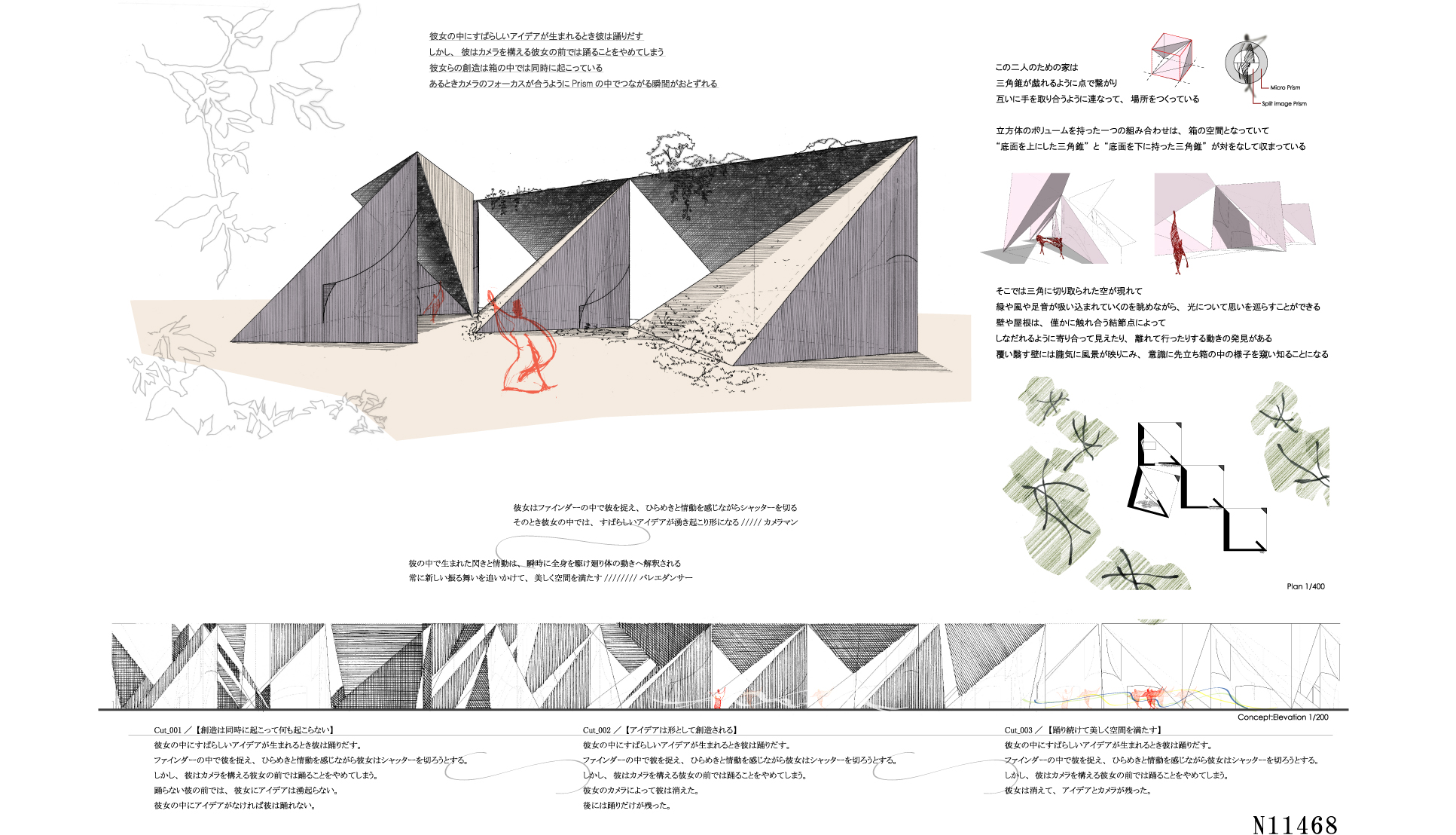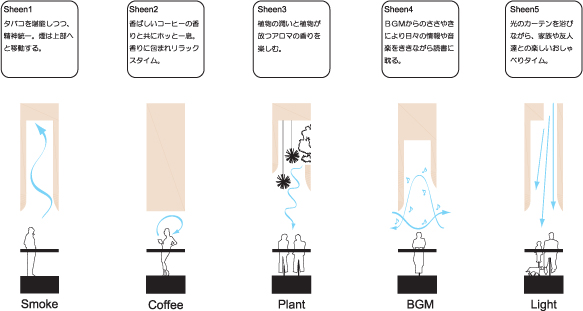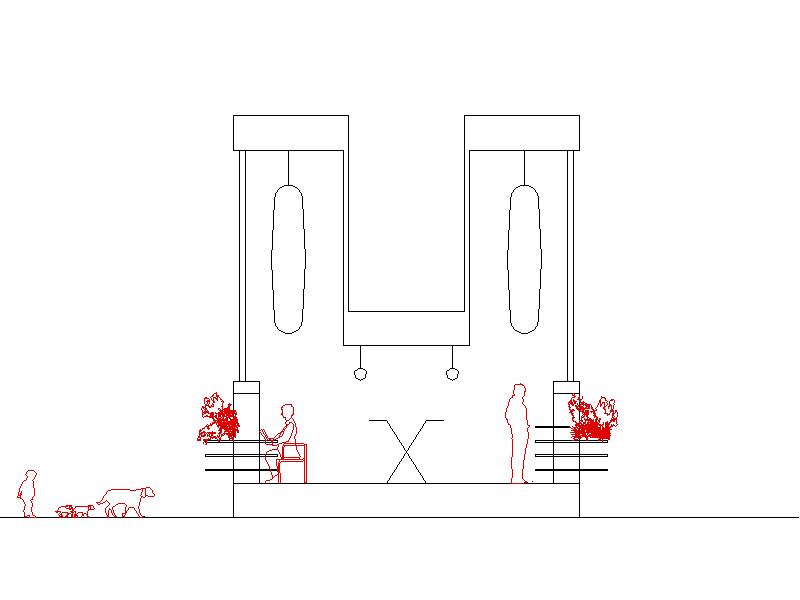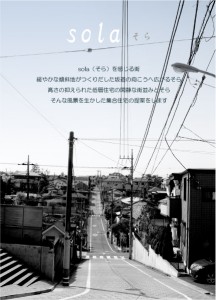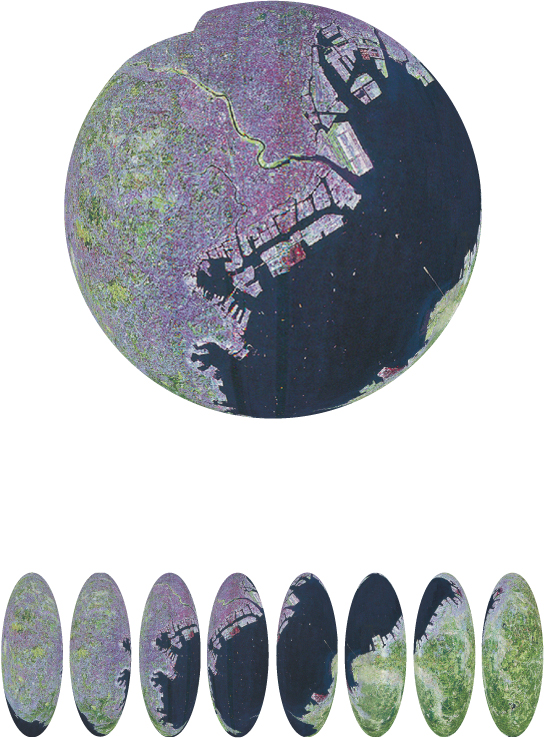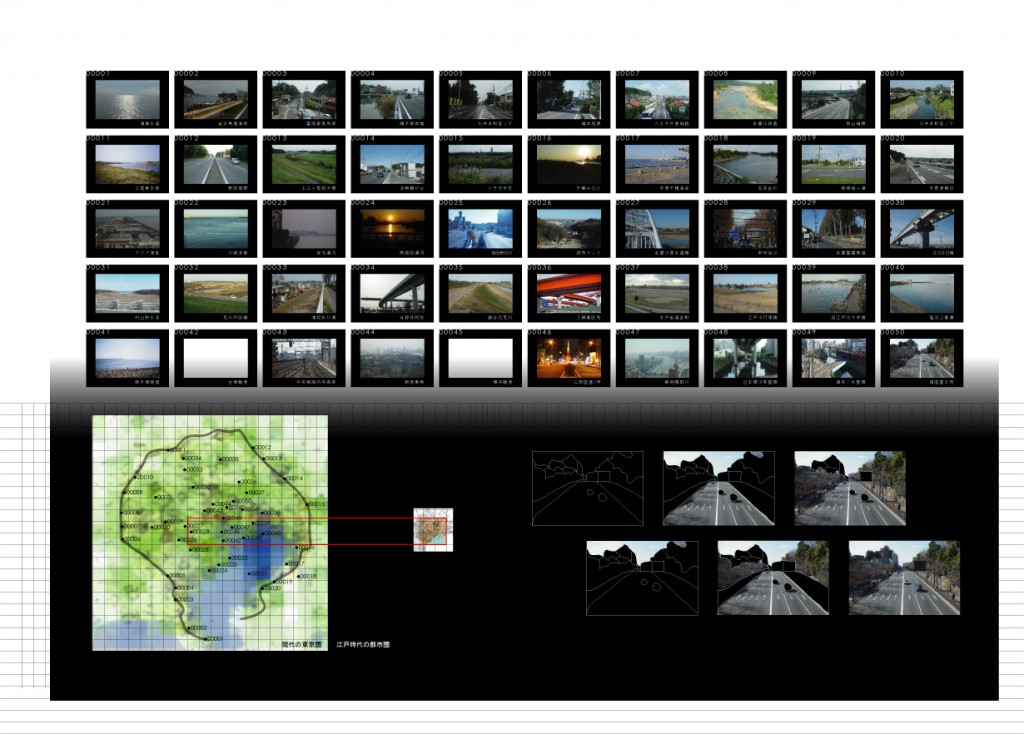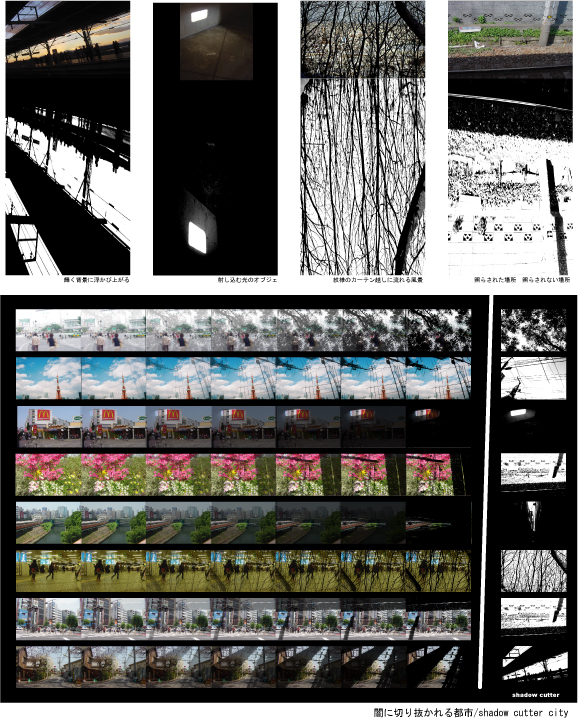小説家、作家の文章の巧さを決定づけるもののうち、特に比喩表現には興味がある。
フィルムに風景を焼き付けるフォトン(光の粒子)のごとく伝えたい内容を浮き彫りにしていくようなテクニックであるし、
境界線を曖昧にすることでよりリアルに感じさせるテクニックでもある。
レトリック研究の足元にも及ばないだろうけども、まずは『1Q84/村上春樹』の比喩表現を集めて、並べてみたい。
昆虫マニアが似たような羽虫を一つ一つ丁寧に箱の中に並べていくように、まずは収集してみよう。
もうこれで完成だよと言えるくらいまで敷き詰めたら、その箱は昨日までのガラクタではなく新しい意味が備わっているはずだ。
さっきまで散り散りに光っているだけだった星空が、一度星座の形を覚えるともう二度とノイズとして認識しないように。
<1Q84 book1/村上春樹>
蝶を起こさないようにとても静かに。
気球に碇をつけるみたいにしっかりと。
まるで舳先に立って不吉な潮目を読む老齢な漁師のように。
つややかに誇らしそうに光っていた。
常に大事な物事をひとつ言い残したようなしゃべり方をする。
ミニチュアの架空の雲みたいにぽっかり浮かんでいた。
その小さな雲を追いやるように発言した。
退役した参謀が過去の作戦について語るような口調で。
開いた窓から一群の鳥が部屋に飛び込んでくるみたいに。
ねじれに似た奇妙な感覚。
体の全ての組成がじわじわと物理的に絞り上げられているような感じ。
首の後ろのしわが太古の生き物のように動いた。
書物の大事な一節にアンダーラインを引くように。
大事な合言葉を暗記するみたいに。
その両目は優秀な甲板監視員のように、怠りなく冷ややかだった。
とめていた紐が切れて仮面が剥がれ落ちたみたいに。
不安定な秤のようにふらふらと揺れていた。
大きな洪水に見舞われた街の尖塔のように。
世界はゆるい粥のようにどろどろとして骨格を持たず。
普段は開ける事のない抽斗の奥から引っ張り出してきたような微笑だった。
小松は出来のいい生徒を前にした教師のように目を細めた。そしてゆっくりと肯いた。
身体が大きく早起きの農夫のような目をしていた。
指揮者がタクトで独奏者を指定するように
深い穴に逃げ込んだ臆病な小動物みたいに、なかなか外に出てこない。
マスコミは夕暮れどきのコウモリの群れみたいに頭上を飛び回るだろう。
バスケットボールから空気が抜けるときのように。
収穫前にイナゴの群れを畑に送りつけないでくれと、神様にお願いする農夫のように。
見た事のない風景を遠くから眺めるみたいに。
口にするひとつひとつの言葉に、サイズの合った楔のような的確な食い込みが感じられた。
職業的な笑みを適当な句読点のように浮かべ、仕事に戻って行った。
それは意味性の縁を越えて、虚無の中に永遠に吸い込まれてしまったようだった。
冥王星の脇をそのまま素通りしていった孤独な惑星探査ロケットみたいに。